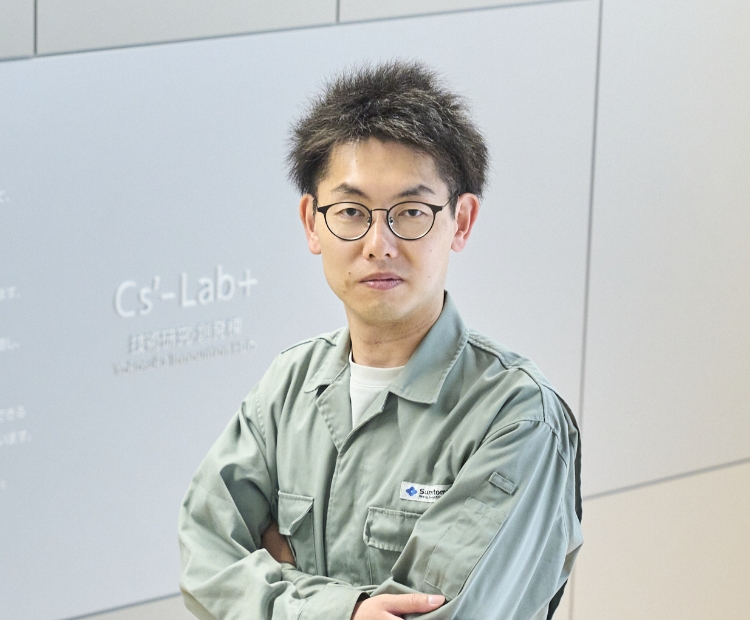
技術系|新卒採用研究開発
環境、品質、生産性。
製造の未来を見据えた加工技術の提案者に。
技術本部 技術研究所
2013年入社/結晶材料工学専攻 修了
※所属、部門は取材当時のものです。
研究の軸は「効率化」。
熱処理と機械加工技術の開発に取り組む日々。
私の所属する材料技術部では、材料設計・加工技術・材料評価技術の3本柱で、我々機械メーカーの根幹であるものづくりを技術面から支える研究開発を行っています。私はその中で加工技術グループのリーダーを務め、熱処理と機械加工を主軸に研究開発を推進しています。
私はものづくりにおいては、「効率化」が重要であると考えております。品質担保は当然であり、その中で如何にプロセスを効率化し、環境負荷低減や生産性向上を達成できるか、この考えが競合優位な技術の獲得に繋がると考えています。例えば熱処理工程はエネルギー消費や二酸化炭素排出が大きいため、低温・短時間・再利用可能な効率的なプロセスの確立が急務です。また、企業としては環境対応と両立しつつ収益性を確保する無駄のない効率的な生産技術が求められます。「この加工法に変えれば強度が向上し、時間短縮も可能」「この処理工程を省いても特性は維持できる」——。そうした具体的な改善提案を通じて、部門のものづくりに貢献しています。
大型構造物の破損調査を経験。
ベテランの背中に学んだ、調査技術と姿勢。
材料技術部では、各部門からの依頼で製品の破損原因調査も行っています。設計・製造・使用環境を考慮しながら破損要因を分析し、改善提案につなげる重要な役割です。強く印象に残っているのが入社7年目で担当した船から石炭を陸揚げする大型構造物の破損原因調査案件です。
この時私の大きな支えとなったのが、経験豊富なベテランの存在でした。調査の流れとしては破損部品の外観を詳細に観察し、破損原因の仮説を立て、それを検証するための調査計画を立案、計画に基づいた金属組織等の調査データから破損原因を究明します。外観観察での鋭い視点や豊富な経験からの仮説立案、調査データの解釈等々、取り組む姿勢含め、学びの多い機会となりました。また、我々が究明した破損原因がアンローダーの使用環境で生じ得ることを技研内の解析の専門家が検証し、多角的な視点で原因究明につながる根拠を示しました。その結果、お客様が納得してくれたことはもちろんのこと、対応力を業界で高く評価頂いたと聞いています。本件を担当した経験は今も調査の姿勢に大きな影響を与えています。

現場に足を運び、技術を磨く。
製造業全体の最適化を目指して。
印象深い経験の一つが、ドライブテクノロジーズSBUとともに行った熱処理工程の見直しです。約8カ月にわたり製造現場に入り込み、生産技術部や商品開発部と連携してプロセス改善に取り組みました。
この時得られたのは、技術的な学びだけでなく、現場でのものづくりの事情を理解することの大切さでした。現場で何が起きているのか、問題が生じる原因は何なのか、改善への障壁は何なのかを理解することで、より実効性のある技術提案ができるようになると感じました。現在、製造現場の環境負荷低減に向けて取り組んでいますが、これは研究所だけで完結するものではありません。現場に根差した、納得感のあるソリューションを提示できるよう、引き続き提案を重ねていきたいと思っています。
このように、現場と研究所の双方をつなぐ立場としての責任とやりがいを日々感じています。技術開発は一人では成し遂げられません。設計、製造、評価を担う多様な部署と連携しながら、知見を積み重ねていくことが重要です。加工技術はものづくりの土台を支える重要な要素であり、私たちの取り組みが会社全体、ひいては製造業全体の革新に寄与するものと考えています。今後も視野を広く持ち、技術を通じた全体最適を目指して挑戦を続けていきます。
1 day Schedule
- 9:30
- フレックス出社
- 10:00
- 部内の破損調査案件に対するフォロー会
- 11:00
- 研究開発課題①に関する打合せ
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- グループ定例打合せ
- 14:00
- 研究開発課題②に関する打合せ
- 15:00
- 部門との協業に関する進捗打合せ
- 16:00
- 熱処理技術協会から発足している
研究部会WGメンバー(社外)とのWeb打合せ
- 17:00
- 各種資料作成
- 18:30
- 退社